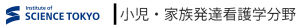当分野について
ホーム › 当分野について
教授挨拶
2025年(令和7年)4月より、当分野の教授に着任いたしました佐藤伊織と申します。小児・家族発達看護学分野は、平成13年より現在の名称となり、乳幼児精神保健をその基盤として発展してまいりました。今後も家族ライフサイクル・家族関係・育児/介護/家事といったキーワードを中心に、分野メンバーで一体となって、医療・支援を必要とするさまざまなこどもと家族のことを考えていきます。
当分野では、患者個人・家族員個人ではなく、家族全体のWell-being/functioningを志向して研究・教育を進めてまいります。看護師養成教育にあっては、看護の対象である家族の中で何が起きているのか、それならばどうすればよいかを考えられる力を養成します。大学院教育や研究活動においては、家族の中で、誰か一人にとっても全体にとってもよりよい看護を探求できるよう、複数の家族員から情報を得て解析・解釈する方法論を踏まえ、臨床現場や当事者コミュニティと共に活動を進めていきます。
教授就任挨拶(→東京科学大学公式サイトへ)
授業紹介代わり(→東京大学勤務時の模擬講義)
当分野では、患者個人・家族員個人ではなく、家族全体のWell-being/functioningを志向して研究・教育を進めてまいります。看護師養成教育にあっては、看護の対象である家族の中で何が起きているのか、それならばどうすればよいかを考えられる力を養成します。大学院教育や研究活動においては、家族の中で、誰か一人にとっても全体にとってもよりよい看護を探求できるよう、複数の家族員から情報を得て解析・解釈する方法論を踏まえ、臨床現場や当事者コミュニティと共に活動を進めていきます。
教授就任挨拶(→東京科学大学公式サイトへ)
授業紹介代わり(→東京大学勤務時の模擬講義)

研究テーマ
下記のとおり、小児看護や家族看護に関連する内容であれば、特にテーマを限ってはいません。こどもや家族に何が起きているのか、どうすればよいかということを、文献やデータに基づいて科学的に考えていくことを旨としています。
・ 小児看護学全般、家族看護学全般
・ 小児看護学全般、家族看護学全般
Child and Family Nursing
・ 疾患をもつこどもとその家族の理解と支援
Understanding and supporting children with illnesses and their families
・ 障害のあるこどもをもつ家族の育児・介護の支援
Understanding and supporting the parenting and caregiving experiences of families raising children with disabilities
・ QOL・アウトカム指標、評価尺度の開発とそれを用いた看護システムの構築
Development of quality of life and outcome measures, and the design of a nursing care system based on these assessment scales
・ システム的な相互作用を明らかにする統計学的方法論の検討・活用
Investigation and utilization of statistical methods for exploring systemic interactions
研究方法としては以下が(この順で)多いように思われます。しかし、既存の研究方法にとらわれる必要はなく、研究目的に沿って最適な研究方法を開発していくことも研究者の仕事です。
・質問紙や調査票によって定量的データを収集し、統計学的に解析する研究
・インタビュー等によって定性的データを収集し、質的に解析する研究
・文献(原著論文から一般書籍などの資料まで)を収集・整理・分析した研究
・実践現場で患者・家族に起きていることを定性的・定量的に記述する研究
研究方法としては以下が(この順で)多いように思われます。しかし、既存の研究方法にとらわれる必要はなく、研究目的に沿って最適な研究方法を開発していくことも研究者の仕事です。
・質問紙や調査票によって定量的データを収集し、統計学的に解析する研究
・インタビュー等によって定性的データを収集し、質的に解析する研究
・文献(原著論文から一般書籍などの資料まで)を収集・整理・分析した研究
・実践現場で患者・家族に起きていることを定性的・定量的に記述する研究

ゼミ
ゼミを週1回開催しています(大学院&卒論生)。
原則として水曜の午前中で、大学院生による研究の進捗発表、卒論生による研究の進捗発表、論文抄読とクリーティク、教員による講義等を行っています。
ゼミ(Seminar)は、少人数制の演習形式の授業のことで、特定のテーマについて主体的に研究する者が集まって、互いを尊重し合いながら議論し理解を深めていくことで、幅広く研究について学ぶことのできる場です。多様な人々が集まって、(教える・教わる関係ではなく)自由に意見を交換できる、新たな気づきを得られる場を目指しています。
原則として水曜の午前中で、大学院生による研究の進捗発表、卒論生による研究の進捗発表、論文抄読とクリーティク、教員による講義等を行っています。
ゼミ(Seminar)は、少人数制の演習形式の授業のことで、特定のテーマについて主体的に研究する者が集まって、互いを尊重し合いながら議論し理解を深めていくことで、幅広く研究について学ぶことのできる場です。多様な人々が集まって、(教える・教わる関係ではなく)自由に意見を交換できる、新たな気づきを得られる場を目指しています。